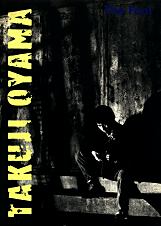 部屋に戻ると空気の色が変わっていた。 部屋に戻ると空気の色が変わっていた。
俺は鍵をベッドに放り投げ、両手を腰に当てて部屋の中を見渡した。確かに何かが違っている。床の上に新聞の切り抜きがふたつ。アクション映画の俳優がロケの最中に大怪我をしたってやつと、どこかの会社の求人広告。ターンテーブルの上にはトム・ウェイツが乗せられっぱなしで、本棚から本が2冊消えている。ボリス・ヴィアンと大友克洋だ。あの子の仕業に違いない。
俺はため息をついて留守番電話の赤いランプを青に変え、煙草に火を点けベッドに腰を降ろし、そいつを聞き始めた。
ピ——ッ 「明日の打ち合わせは1時からになりました。遅れないようによろしく、ということで」
ピ——ッ 「こちらは奥田書店でございます。ご注文のゼルダ・フィッツジェラルドの本が届きましたので、お知らせしておきます」
ピ——ッ 「おめえってやつは一体いつ電話すりゃいるんだよ。二度と電話してやらねえからそう思え!」
ピ——ッ 「もしもし?」
あの子だ。
「……こんなもの電話にくっつけて、安心なんかしちゃってるんでしょ。どうせ朝方戻ってきて、冷めちゃって古くさくなったあたしの声を、両手で転がして遊ぶつもりなんでしょ。そうやっていつも大事なことを後回しにしちゃうのね」
うん。あの子はなかなかの詩人だ。
「……ねえ、本当はそこにいるんじゃないの? いるんでしょ? 出なさい!」
そいつぁ無理だ。あの子は3秒の沈黙の後、年頃の女性が口走るとはとても思えない悪態をついて(バッキャローって言ったんだぜ)電話を切った。ピ——ッ
やれやれ、またすれ違いだ。俺は煙草をもみ消し、キッチンへ行ってグラスにバーボンを注いだ。
あの子の言うことは半分当たっている。部屋にいないって理由で留守番電話をつけてはみたものの、忙しさにかまけて返事の電話なんか一度だってしたことがな
い。そうこうしているうちに、俺はそれほど多くもない友人達への不義理をくり返している。何だかこいつをつけたおかげで、ますます人間嫌いになってしまいそうだ。
この街に住みついて4年、今の仕事を始めて3年3ヶ月、留守番電話をつけて半年、あの子と知り合って2ヶ月。俺はあの子からの電話を5回も取り損ねた。おまけにあの子は気が短いときてる。何も好き好んですれ違っているわけじゃないが、あの子に言わせれば大事な用件で電話する時に限って、受話器からは俺の素気ないメッセージが流れてくるらしい。
「俺はいません」
もっともあの子の大事な用ときたら頭を抱えるくらいくだらないものばかりだ。例えば、あの子の飼っている犬のT・S・ガープが夜中じゅうくしゃみをしてると
か、新聞の契約を半年分したらカメラをくれたとか、あの子の妹に恋人ができたんだけど、その男がバンドマンだったんで別れさせようとしているとか、飲みに行った店で声をかけてきた男がミッキー・ロークに似てたとか、今月はちょっと送れてるとか……いやはや、とにかく女にとって世の中は大事なことだらけだ。
俺はアスピリンを3錠バーボンで飲み下し、ラジオのスイッチを入れ、FENに合わせた。トップ40のカウントダウンが12位 までいったところだった。ベッドに戻ってかたわらのテレビを音なしで点けると、モノクロの映画が流れ始めた。テレビの脇のブライダルベールの白い小さな花が、夜だというのにつぼみ忘れて咲いている。
電話が鳴った。夜中の電話っていうのはいつだって突拍子もなく、そして押しつけがましく鳴り始める。俺は、こんな時間に電話をかけてくるやつらの顔ぶれをリストアップしながら電話に近づいた。もちろんそのリストのトップにあの子の名前はあがっている。俺はたっぷり8回呼びだし音を聞いて受話器を取った。
「……いたのね」
やっぱりあの子だ。この声のトーンからすると、どうやら宣戦布告らしい。俺はベッドに深々と腰を沈め、長期戦への体勢を取った。
「あなたのことが分からなくなってきたわ」
「そう?」
本当はこう言ってやりたかった。
ねえ、俺達まだお互いの2ヶ月分しか見せ合ってないんだ。俺は君のことをほとんど知らないし、君は俺のことをなあんにも分かっちゃいないんだ。
だけどいきなりストレートをくりだすと、相手を本気にさせてしまう恐れがあ
る。
「あたし、さっきも電話したのよ」
「知ってるよ。大事な用件だったんだろ?」
「そう、とても」
「聞くよ」
俺は受話器を耳から5センチ離し、バーボンを一口飲み、あの子の言葉を待っ
た。
「あなたと別れようと思うの」
ストレートだ。俺は思わずむせて咳こんだ。
「あなたがそこらへんにゴロゴロしてる優しいだけの男じゃないってことは、この2ヶ月でよくわかったわ。だけど女っていうのは、嘘だとしてもひと握りの優しいセリフが聞きたいものなのよ」
「……」
「あたし達、おんなじ所でおんなじことをやってても、きっと頭の中では全然違ったことを考えてるのよ。テーブル越しにあなたと話してると、まるで長距離電話でもしてるみたい。たまには本音を吐いたらどう?」
俺はあの子の声を聞きながら、あの子のブラウスのいちばん上のボタンまでの長い道のりを思い出していた。
「聞いてる?」
「聞いてるよ」
「あたし達の接点ってどこにあるの?」
「ベッドの中」
「ふざけないで」
気がつくと、グラスが空になっていた。
「俺は自分の気持ちを人に伝えるのがヘタクソなんだよ」
「知ってるわ」
「君に話したいことが山ほどある」
「だけど?」
「そう。だけど、どんな風に話すのが一番いいのか分からない」
あの子はしばらく黙りこんだ後、皮肉たっぷりの声で言った。
「詩でも書いたら? そしてそれに曲をつけて歌うのね。きっと売れるわよ」
「そいつぁ名案だ!」
あの子はとうとう頭の線が切れたらしく、さっきの留守番電話と同じ悪態をついて(バッキャローだ)電話を切った。
俺はゆっくりと受話器を置いた。キッチンへ行きグラスに2杯目のバーボンを注いでテーブルへ戻り、今日買ってきたばかりのノートを開いた。そして煙草に火を点けながらペンを取り、そこに新しい詩のタイトルを書きつけた。
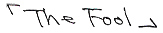
|