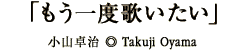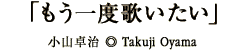|
薄ら寒い場所だった。人の姿は見えず、コンクリートと金網がモノクロの風景を彩っていた。僕はジャケットの襟を立てて辺りを見回す。強い風がドウと吹き、それが誰かの叫び声のように耳を振るわせた。
1990年3月、少年に保護観察の処分が降りたことを知り、僕は事件が起きた浦安の駐車場へ行ってみた。不気味に静まりかえった場所ではあったが、ここで1人の尊い命が途絶えたとは、そして1人の少年の10ヶ月に渡る闘いが始まったとは、想像しにくかった。
事件を知ったのは、その前年、1989年5月29日のことだった。新聞の小さな記事が目にとまった。「また事件か」とその時は、その程度にしか思わなかった。2日後、事件を起こした少年が中国残留孤児二世だと伝える続報が載った。それでも僕にとって、事件はまだ他人事でしかなかった。
その後、新聞は続報を伝え続けた。テレビのドキュメンタリー番組で事件が取り上げられた。無性にこみ上げてくるものがあった。それが“怒り”だと気づき、僕は戸惑った。遠い存在なはずの少年の事件が、なぜ僕の怒りに変わるのか。
判決はくり返され、裏返り続けた。
そして10ヶ月後に事件が終わった頃、少年の物語は、僕の物語になっていた。
浦安から戻り、僕は図書館へ行き、丸1日かけて新聞の縮刷版をめくり、事件に関する記事を探してもう一度読んだ。何が自分を動かしているのか、なぜこんなことをしているのか、と自問自答しながらページをめくった。曲にしたいなどとは考えていなかったと思う。経過を伝えるためだけの文字の向こうから、少年の慟哭が聞こえてきた。それが僕の叫びと同化した。その時初めて僕はギターを手に取り、ひと晩かけてこの歌を作った。
WASPとは、ホワイト・アングロ-サクソン・プロテスタントの略だ。いわば白人の中で支配階級と言われる人種のこと。黄色いワスプとは、僕達日本人のことだ。
1990年3月31日、九段会館のライヴで初めて〈YELLOW WASP〉を歌い、その時のライヴテイクを自主制作としてカセットでリリースした。内容的に、メジャーからリリースできる可能性はなかった。しかしどうしても、僕はこの歌を聴いてほしかった。歌える限り、ステージでこの歌を歌った。
事件を担当した弁護士から、この歌が本人の元に届いたと間接的に聞いた。彼はこう言ったという。
「これは俺達の歌だ」
僕にはそれが心から嬉しかった。
1994年、《ROCKS!》のプロジェクトの時、この歌をCDとして残したくて、僕はもう一度レコーディングにトライした。だがやはり結果は辛いものだった。自主規制という壁に阻まれ、マスターテープは倉庫の奥にしまい込まれた。
それから何年もの間、僕はこの歌をほとんど歌うことはなかった。意識的に自分から少し遠ざけていた。
1997年の秋、僕は国際基督教大学の学園祭で行われた、帰国者のためのセミナーを聞きに行った。そこで事件を起こした少年(もうその時期、少年ではなかったが)に会えることになっていた。だが残念なことに会うことはできず、彼と電話で話した。
「あんな歌を歌う男がどういうやつなのかって、会いたかったんですよ」
そう彼は力強い口調で言った。
歌は人を勇気づけたり励ましたりするパワーを持っているが、時として、人の傷をえぐるような、とどめを刺すようなマイナスのパワーも持っている。僕は彼と話しながら、この歌が少なくとも彼の傷口を開くようなことだけはしなかったことを改めて知り、彼がこの歌を好きでいてくれたことを知り、心底嬉しく思った。
世の中にはたくさんの歌がある。そのほとんどがラヴ・ソングで、僕ももちろんラヴ・ソングを作る。だが大切なことは、それだけが音楽じゃないということだ。音楽は、もっともっと大きなパワーと可能性を持っている。
ビートに乗せて踊るための音楽がある。腰を動かす音楽があるのなら、心を動かす音楽だってある。そもそもそれこそが、音楽が生まれる理由だ。
文字通り“音”を“楽しむ”ことだけを音楽だというのなら、この歌が音楽と呼ばれなくてもかまわない。人の心を揺さぶるもの、それが僕にとっての音楽なのだから。
今年のツアー「Looking For Soulmates」の初日の5月29日(事件が新聞に載って11年目の同じ日)、僕はひさしぶりに〈YELLOW WASP〉をステージに乗せた。この歌がまだ生きているかどうか確かめたかった。歌は少しも風化していなかった。その場にいたお客さんの心に伝わっていくのがビリビリと分かった。もう一度歌いたい、CDとしてリリースしたい、そう思った。
紆余曲折、この歌は「わがままレコード」というインディーズ・レーベルからリリースされることになった。
僕は事件を起こした少年のすべての行動を正当化したいのではないし、1人の命が失われたことを忘れてもいない。この歌が、たくさんの人間の痛みを伴うことは承知している。それでもこの歌を歌いたいのは、僕自身を含む人間の心の中の暗黒に気づいてしまったからだ。それを伝えることが、この歌の役目だと、この歌を作った僕の役目だと思うからだ。
この歌が、人の心に何かを伝えられると信じているからだ。
2001.02.10
▲
|